自分よりも歳の若い人や
同じ年齢ぐらいの人が
亡ったことを聞くと
人の命は尊くなんて儚いのだと
思い知らされます。
本書ではまだ、十六歳の少女の死を
看取った著者の
死に行く人のために何ができるかを
医師として痛感した経験が綴られて
います。
私たちは、
まさに今死にゆく人に対して
何ができるのでしょうか。
死に様は生き様
昭和十二年、
著者が医師となり最初に受け持った
患者は「結核性腹膜炎」十六歳の少女
でした。
衰弱もひどく、母親と一緒に
病院を訪れ、入院して治療をうけます。
彼女は家が貧しく小学校を
出るとすぐに女工として働きて
いたところ、病気になってしまった
のです。
治す術がなく、衰弱していく少女
当時は結核に効くストレプトマイシンも
なく、腹痛や便秘や下痢の対処ぐらいしか
できませんでした。
効果の期待ができないことでも
試しにやってみると言うことを
することぐらいしか
著者も医師としてできないのです。
それなのに、
ときどき採血などの苦痛を伴う
行為をしなければなりません。
病気の症状の苦痛も
検査の苦痛にも嫌な顔ひとつしない
少女でした。
日曜を寂しがる少女
父親のいない少女は母とともに
紡績工場の女工として
働いていました。
あの、過酷な条件下で働かされ
結核などの病気が蔓延しやすかった
「女工哀史」に出てくるような
状況だったのでしょう。
母親は娘の入院費用や生活費を
稼ぐために
娘の病気の世話に来院して
付き添うことが難しく
二週に一回くらいしか見舞いに
くることができません。
普段の日は著者が来て
少女の腹痛で苦しく時には
病床を訪れ、
どうしても治らない時は
“麻薬“を使って苦しいを和らげる
ことをしていましたが
著者は敬虔なクリスチャンであり
日曜日には教会の礼拝に朝から出席
しているので
病院には行かなかったのです。
少女は八人の大部屋で過ごし
他の人は日曜でも家族や医師が
来ているからなのが
「日野原先生は日曜だけは
病院に来られないのよ」と
他の医師に寂しそうにしていたようで
さらに、少女が腹痛で
苦しんでいても当直医は
少女にモルヒネを使わないことが
多く、
(当時は“麻薬”は使わないように
指導されていたため)
死が迫った患者であっても
医師は、あたかもあと何年も
生きる望みがあるかのように
モルヒネ剤の注射を繰り返すのを
拒むことが多かったのも
主治医である著者でなければ
少女の苦痛を取り除くことが
できなかったこともあって
少女は著者を渇望していたの
かもしれません。
死を受容する少女
嘔吐が続き、彼女の容態は
深刻な状態になってきました。
モルヒネは
二倍の量を使用し、少女の
苦しみを軽くしていくことに
努力していましたが
弱くなってきている脈を
感じながら
時より少女の手を意識的に強く
握り、
「お母さんが午後から来られるから
頑張りなさいよ」と声をかけると
少女は
「先生、どうも長い間お世話になりました。
日曜の来ていただいてすみません。」
「私は、もうこれで死んでいく気がします。
お母さんに会えないと思います。」
「先生、お母さんのは心配をかけ続けで
申し訳なく思っているので
先生からお母さんによろしくお伝え
ください。」と
著者に向かって合掌したのです。
死を受容した少女の感謝と訣別の言葉
に対して
著者は
「あなたの病気はまた良くなりますよ
死んでいくことはないから元気を
出しなさい」と言ってしまいます。
そのとたん、少女は急変し無くなって
しまったのです。
死にゆく人への対応
著者は今になって思います。
なぜ、
「安心して成仏しなさい」と
言わなかったのか?
「お母さんには、あなたの気持ちを
充分に伝えておきますよ」と
なぜ、言えなかったのか?
脈を診るより
どうしてもっと少女の手を
握ってあげなかったのか?
著者はこの少女の死を受容し
美しい言葉で決別した
この事実を後からくる後輩医師に
伝えたいと思っている。
医学・看護がアートであることは
このような死に対決できる術を
医学・看護に従事するものが
持つことではないでしょうか。
To cure sometimes
To relieve often
To comfort always
これは古き時代の西洋のある優れた
臨床医が遺した言葉を著者はここで
引用しています。
癒すことは時々しかできなくても
和らげることはしばしばできる。
しかし、病む人の心の支えとなることは
いつでもできることであると
著者はこのことを強く心に命じ
これから600もの“死“に向き合って
いくことになります。
まとめます
著者はこの少女の死から
日曜も必ず病院に出かけ
患者を一度は診ると言うことを
習慣化されました。
今回の場合は、少女が短すぎる
生涯を終えるにあたっても
ジタバタせず穏やかに
周囲の人たちに気を配り
感謝しながら亡くなった
ことで
著者自体も“死“とは
どうゆうものかと考える
きっかけとなったのでしょう。
“死“は“生“と切り離されたものでは
なく、
生きていることの
延長の“死“であること、
よく死ぬためにはよく生きなかければ
ならないこということを
知っておかなくてはなりません。
この少女を看取って
著者も死を受容した患者に対して
「安心して死んでゆきなさい」と
言ってあげられる医師も
病気を治し、延命するのと同じように
必要であると本書では示しているのです。

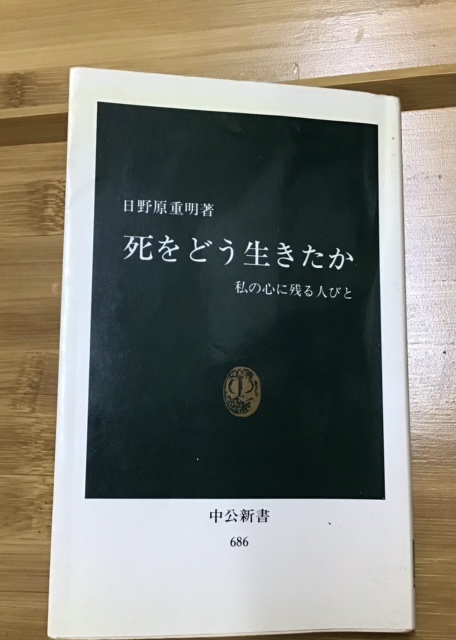


コメント