この著書の主人公の栗原一止は
地域の救急医療を担う医師のひとりです。
長時間労働、寝不足、休日返上は
当たり前。
しかし、そのことについては
職業がら覚悟はできているのです。
しかし、医療の限界「治らない患者」を
見続ける苦悩はなかなか拭いきれる
医師は少ないです。
そんな中、ふと
自分がそんな患者にこそ“支えられている“
と言うこと気付くのです。
医局に属さない医師は胡散臭い?
本書の主人公の一止(いちと)は
信州の本庄病院に勤める医師です。
ここは大学病院ほどではないですが
400床ほどのそこそこ大きな病院で
患者を24時間、365日受け付けて
いる病院です。
一止はまだ、5年目の医師なので
大学の医局に属して
最先端の医療を学びながら
後々は医局の意向(都合で)
いろんな病院に派遣(飛ばされる)されて
いくのですが
一止は大学の医局に属さない医師で
この職場は本人の意志で勤めています。
早くから「最先端医療」から離れると
腕が上がらないのもありますが
何か問題を抱えた医師ではないかと
胡散臭く思われるほど
若い医師が医局に属することが
当たり前の中
一止はそれをせず田舎の中規模病院に
勤め、寝食を忘れて仕事に邁進して
います。
何をもって良い医者とするのか
医者の中にも
より高度な医療を目指すものと
野に下る(地域医療)ものもいる。
一止は後者だったのです。
多忙の中とにかくより多くの患者を
見ていかなければならない
地域医療に高度医療がどれだけ
必要か疑問に思っていることが
一止が医局に属さない理由の一つなのです。
では「良い医師」とはどんな医師の
事を言うのか
それが至上の難題であり
一止をはじめ医師が考え続けなくては
ならない事なのです。
「お前は何もしてくれなかったじゃないか」
すでに全身に転移が見られた田川さん。
全身の痛みのコントロールがうまく
いきません。
痛み止めに麻薬のモルヒネを使いますが
それが鎮痛効果が得られず
副作用(呼吸抑制)ばかり出てしまいます。
助かる見込みがなくても
苦痛を取り除いてあげるのも
医師の勤めなのですが
薬を強くするといった単純なことでは
ないのでそれもままなりません。
医師の苦労とは裏腹に周りの
家族やスタッフに焦りが見られます。
「先生、痛みを何とかして
あげられないんですか」と…
結局、苦痛を満足に取り除くことが
できず
田川さんは亡くなってしまいます。
その時、孫に当たる少年が一止に
「お前は何もしてくれなかった」と
そんなふうに言われたような
気がしたのでした。
無為、無策、無能、無力、無駄、無用
水無さんや少年にとっては、
あれが偽らざる感情なのであろう。
助けてくれるはずの医者が
なにもしてくれない。
偉そうに顔で歩き回っているくせに
痛みひとつうまく治療してくれない…
「神様のカルテ」夏川草介著
一止の頭の中が「無」という文字が
これみよがしに強調される…
助けてくれるはずの医師が
病気を治すどころか
苦痛さえも満足に取り除くことが
できないでいる。
医師が何度も経験する
この無力感に加え、さらに
過労とストレスが重くのしかかって
くる瞬間なのです。
家族に対しての労りの言葉を忘れる
一止は妻のハルにこのような時は
何も言わなくても察してもらい
癒してもらっているが
ハルに対しての労りの気持ちは
一止は後になってから気づく。
「そうだ。ハルさんも長期撮影から
帰ってきたばかりだった」と…
たくさんの患者を救う医師は
その医師の家族にも配慮を強いる
ことになるのです。
細君は懸命に
私を励ましているのである。
胸に積もっていた
泥のようなわだかまりが
静かに押し流されていく。
“なんたる失態だ…!“
私はおのれを叱り付けた。
私としたことがひとり手前勝手に
懊悩し、
気がついてみれば、
長旅からようやく帰宅した細君に
ねぎらいの言葉ひとつかけていない。
ひとり鬱々と感傷のぬるま湯に浸り
固執の酒に酔いしれていただけである。
なんと無惨なひとりよがりか。
「神様のカルテ」夏川草介著
黙ったままそばに座ってうなずく
一縷の望みをかけて
大学病院に治療を打診したが
「余命半年、好きなことをして過ごすように」
でした。
このように言い放たれた
胆嚢癌の安曇さんでしたが
当然、治療見込みがないのですから
大学病院で入院はできません。
これから次々と病気が浸潤し
身体を蝕んでいくと予想される
恐怖と不安にひとりで立ち向かうには
あまりにも酷なことなのです。
しかし、現在の医療体制では
“治る人“を優先しても
逼迫している状態なので
仕方がないことでもあります。
一止は安曇さんを最後まで診ると
約束すると安曇さんは
一止に穏やかな表情で
病状の説明を求めます。
癌の大きさや問題点や
今後の予測される経過を話しました。
だだひとつ、「一ヶ月もたない」
ことだけは言いませんでした。
天国より、めいっぱいの感謝をこめて
いよいよ安曇さんの容体は
悪くなってきています。
食欲低下、貧血…
無理に動かせば大出血の可能性も
ある。
そんな安曇さんを屋上に連れ出し
故郷の北アルプスを
見せてあげることにした
一止と看護師たちそして
一止の依頼を受けてハルが用意した
亡き夫との思い出の食べ物の
“文明堂のカステラ“を誕生日祝いだと
言って渡すと箱を握りしめて
涙を流したのです。
こんな生きているうちに
幸せになっては…
夫に合わせる顔がありません…
こんなに…
なんと言っていいのか…」
「神様のカルテ」夏川草介著
安曇さんはそれから2日後に
亡くなりました。
夫からのプレゼントの帽子の側に
「夫が亡くなってから30年で
もっとも楽しい時間を過ごせました」
と一止たちへの労いの言葉が
添えられていました。
治りもしない患者に寄り添ってくれた
感謝の気持ちだったのです。
まとめます
「治らない」患者を診ることほど
医師にとって屈辱的なことは
ないのです。
しかも、何もできず朽ち果てて行く
人間の姿を目の当たりにしなければ
いけないほどストレスなことは
ないのです。
その苦悩は長時間労働や寝不足などの
苦痛の比ではないのです。
その感覚がある意味麻痺しないと
医師自身、自分の存在を維持する
ことができないのかもしれません。
大学病院は高度な医療を施し
また、教育、研究の最先端を担う
大切な組織であります。
安曇さんのような「治らない」患者を
ある意味“切って“しまわないところでも
あります。
同じ医師なら最先端の医療を施し
「治る」患者を救う仕事の方が
望まれるでしょう。
しかし一止のように踏みとどまり
その大組織から漏れ出てしまった
患者を人生ごと救ってあげれる
医師も確かに必要なのです。

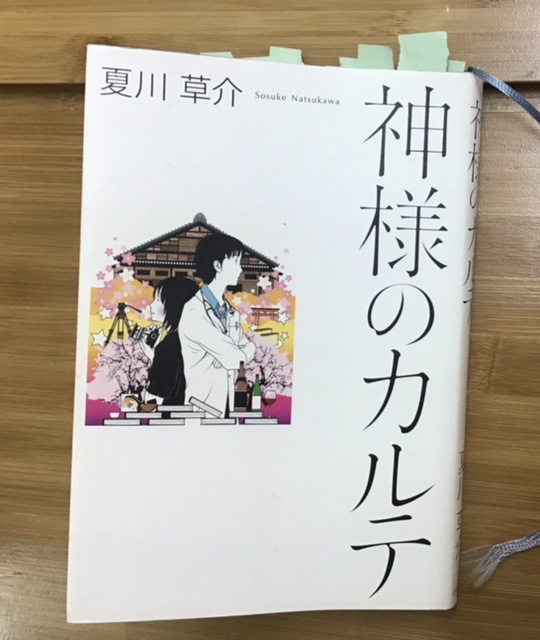


コメント